※この記事は、障害年金を受け取りながら「自分なりの再起の道」を模索してきた僕個人の体験に基づいています。
「働ける=偉い」「稼ぐ=正しい」と言いたいわけではありません。
働くことが難しい方、今は休養が必要な方、あらゆる状況の方を否定する意図はまったくありません。
むしろ、「いま不安の中にいる誰かが、“こういう考え方もある”と感じてもらえたらいいな」――そんな気持ちで書いています。
関連記事です。
はじめに|「堂々ともらえない」のは、僕だけ?
「老齢年金はみんなもらってる」
「でも、障害年金はなんとなく言いづらい」
これって、僕だけなんでしょうか?
長年働いて納めた保険料。
それで受け取ってるのは“当然の権利”のはずなのに――
どこかでずっと、「すみません、ありがとうございます」と言いながら受け取っている自分がいました。
それは、
社会の空気?
制度のせい?
自分のプライド?
このモヤモヤの正体を、今こそちゃんと掘り下げてみようと思います。
第1章|老齢年金=“労い”、障害年金=“同情”のような視線?

老齢年金は、「働ききった人の権利」「国が与える報酬」のように受け止められがちです。
「年金生活に入りました」と言っても、
誰も疑問を抱かないし、引け目も感じません。
でも、障害年金は?
- 働き盛りでの受給
- 外見では障害がわからない場合も多い
- 「働けるのに受け取ってるのでは?」という誤解を受けやすい
その結果、「ありがとう」じゃなく「申し訳ない」気持ちで年金を受け取る人が多いのが現実です。
第2章|“制度の曖昧さ”が生む「自己規制」という壁
老齢年金は明確です。
- 資産がいくらあっても支給OK
- 働いても原則支給(在職老齢年金の調整はあるが明文化されている)
一方、障害年金はどうでしょう?
▽ 厚生労働省の見解:
障害年金は「日常生活能力の制限」が基準。働いていても、等級に該当すれば支給可能。
(出典:厚労省「障害年金Q&A」)
しかし、現場では…
- 就労=改善とみなされ、再認定で等級が下がる可能性
- 主治医の“就労への理解度”で診断書の書き方が変わる
- 申立書の記載内容との整合性が強く問われる
この「曖昧な不安定さ」が、「じゃあ働かない方がいいのか?」という自己規制の心理につながります。
実際、社労士の間でも“就労と障害等級の関係”について見解が分かれるほど、グレーです。
🧭 老齢年金と障害年金の「就労・資産・支給条件」比較表
| 項目 | 🧓 老齢年金(例:厚生年金) | ♿ 障害年金(1・2級) |
|---|---|---|
| 支給の目的 | 長年の就労に対する労い | 障害による生活・就労困難への支援 |
| 支給開始時期 | 原則65歳~ | 障害認定日にさかのぼって支給 |
| 就労の可否 | 働いても原則OK | 働けても支給される場合あり |
| 働くことの評価 | 社会参加として前向きに評価 | 「改善」とみなされることも… |
| 資産や収入の制限 | 資産・年収にかかわらず支給 | 所得制限なし(※福祉手当は別) |
| 支給の安定性 | 原則、生涯にわたり支給 | 再認定で等級変更や支給停止もあり |
| 制度上の明確さ | 条件が明文化されている | グレーゾーンが多く、判断に揺れがある |
| 受け取る側の感情傾向(世間的) | 「堂々としていい権利」 | 「申し訳なさ・遠慮」がつきまとう |
こうして比べてみると、同じ「年金」という言葉でも、その背景や周囲の理解、そして制度の構造そのものに大きな違いがあるのがわかります。
特に「就労してもOK」のはずなのに、「働いたら減額されるのでは?」という不安がつきまとうのは、障害年金特有の曖昧さと空気の壁のせい――。
だからこそ、「制度の正確な理解」と「正しく伝える勇気」の両方が必要なんだと、僕は感じています。
第3章|「もらってるくせに働くの?」という空気の正体
実は、障害年金には収入制限がない(※所得制限があるのは一部の福祉手当や控除)にも関わらず、働くことに対する“空気の壁”は根強いです。
- 「障害年金で悠々自適」と揶揄される
- 「障害者枠で就職=配慮されるべき存在」という無言のラベリング
- 「それだけ動けるならもう年金いらないでしょ」と言われかねない恐れ
この空気の正体は、たぶんこうです。
社会はまだ、「働けない人」=「年金をもらって当然」
「働いてる人」=「もらう必要なし」という、極端な二元論に縛られている
僕は実際にこう思ったことがあります。
「ブログで収益を得たい。事業所得も得たい。
――この姿を見られたら、“ズルしてる”って思われるんじゃないか?」
でも、本当は違う。
働けるようになったなら、納税者になることで社会に恩返しする道だってある。
むしろそれが“本来の制度の意義”じゃないのか、と僕は思っています。
関連記事です。
第4章|その「後ろめたさ」は、あなたのせいじゃない

もし、あなたも僕と同じように、
- 障害年金を受け取っていることを“誇れない”
- でも、“ずっと依存しているのも違う気がする”
- 少しでも働こうとすると“後ろ指さされる気がする”
そう感じていたら――どうか、自分を責めないでください。
それは、あなたの認識不足でも、努力不足でもない。
ただ制度が曖昧で、
社会がまだ「多様な障害と働き方」に慣れていないだけなんです。
第5章|じゃあどうすればいいのか?僕なりの答え
じゃあ、このモヤモヤの中でどうすれば前に進めるのか?
僕は今、こんな風に考えています。
■(1)制度の正しい理解を持つ
- 障害年金は「就労=即打ち切り」ではない
- 就労=障害の改善とは限らない(特に内部障害や精神障害では顕著)
👉「自分の障害に応じた生活への支援」であることを、まず自分が認識する。
■(2)“発信する側”に回ってみる
後ろめたさに押しつぶされるより、
「こういう生き方もある」と実例を見せることの方が、よっぽど建設的だと今は思っています。
- ブログを書く
- SNSで日々の工夫を発信する
- 同じ境遇の人の声に耳を傾ける
発信は、「堂々としていい」と自分に許可を出す行為でもあります。
■(3)“感謝”はあっていい。でも“卑屈”にはならなくていい
年金を受け取れることはありがたい。
でもそれは“下にいる”ことを意味しません。
感謝と誇りは、同時に持っていていい。
■(4)遠慮せず、「学ぶ」も「稼ぐ」も目指していい
もし、あなたが「どうせ年金をもらってるから…」と学びや挑戦にブレーキをかけているなら、
そのブレーキは、もう外していいと僕は言いたい。
年金は「権利の行使」。
そのうえで、働ける力を少しずつ取り戻し、学び直し(リスキリング)をして、
稼げるようになったら納税して、また社会の一部として機能していくことができる。
これは「ズル」でも「贅沢」でもない。
社会に“再び加わる”という、立派な歩み直しなんです。
関連記事です。
※この章では「障害年金をもらいながら、再び稼ぐことを目指す」という僕個人の考えを紹介しています。
僕の場合は、保険による給付やある程度の金融資産があったことで「減額や停止されても仕方ない」と思える土台がありました。
誰にでもその余裕があるとは思っていませんし、「働くこと」や「再起を目指すこと」が難しい状況の方を責めるつもりもありません。
この記事は、あくまで「こういう考え方・生き方もある」という一例として、必要な人にだけ届けばと思って書いています。
おわりに|僕らは「もらって生きる」のではなく、「立て直して生き直している」

障害年金をもらっている――
その事実は、過去に大きな困難を経験したことの証です。
でもそこで止まらずに、自分の力で生活を立て直そうとしている。
学び直し、働き方を模索し、時には発信しながら――
再起動するように、自分の人生を編み直している。
だから僕はこれからも堂々と書いていきます。
「障害年金をもらいながら、僕は働く」
「リスキリングも、副収入もやっていい」
「それはズルじゃない。再起のための“投資”なんだ」
もしあなたが、同じようなモヤモヤを抱えているなら――
この文章が、少しでも背中を押せたら嬉しいです。
📊 ヘタゴリラの“配当記録”と“損益バトル”はXで更新中!
ブログでは語りきれない、リアルな配当金の推移や
**日経平均との“持ち株バトル”**など、日々の投資ログをXで公開しています。


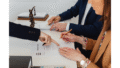
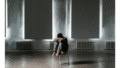
コメント