※この記事では、僕自身の体験と、障害年金制度に関する制度情報をもとに、「年金と仕事の両立」に悩む人へ向けて、ひとつの視点を紹介します。
はじめに──「支えを受け取ること」と「働くこと」のあいだで
障害年金を受け取りながらも、少しずつ働けるようになった──。
そんなとき、真っ先に頭に浮かんだのは「働いたら年金が止まるのでは?」という不安でした。
僕は元・建設業の個人事業主でしたが、事故をきっかけに重度の身体障害を負いました。
そこから、リハビリと筋トレを続け、ようやく“軽作業ならできそう”というレベルにまで回復。
ですが、同時に「直接雇用=年金の減額・支給停止リスクがあるのでは?」という、グレーな不安とも向き合うことになったのです。
この体験を通じて気づいたことがあります。制度と向き合いながら、自分のペースで“次の一歩”を考える──この記事では、そんな視点を共有したいと思います。
関連記事です。
第1章|なぜ「就労」が不安になるのか?制度の“見えにくさ”
障害年金制度のポイントは「労働の実態」にあります。
つまり、
- フルタイム雇用で働いているか?
- 労働時間・業務内容がどれだけ負荷を伴うか?
- 継続性・安定性のある収入か?
こうした観点から「もう障害状態ではないのでは?」と見なされると、支給停止や等級変更の対象になることがあります。
一方で、A型事業所や福祉的就労では、
- 短時間就労(週20時間未満)
- 軽作業
- 支援者の配置 といった要素があるため、“生活に制限が残る中での就労”として認められやすい仕組みになっています。
厚生労働省も、「働いているから即支給停止になるわけではない」と明記しています。 👉 障害年金Q&A(厚生労働省)
第2章|僕がたどり着いた「働き方の選択肢」

僕は最初、A型事業所(就労継続支援)での軽作業を試しました。
これは雇用契約があるため、制度的には“労働”とみなされます。
勤務は、月〜金の9時〜15時。仕事内容は、封入作業や仕分け、清掃、事務補助などの軽作業。
月5万円程度の収入でしたが、「社会に戻れた」という実感を得るには、十分すぎる経験でした。
とはいえ――元・事業主だった自分には、どうしても“水が合わなかった”。
- 言われた作業を、ただ毎日繰り返すことへの違和感
- 周囲との価値観や働き方のギャップ
- 自分の裁量や工夫を発揮できないもどかしさ
そんな積み重ねで、結局3ヶ月で退所しました。
それでも、「働くことは絶対にNGではない」という確信が持てたことは、何より大きかったです。
また、A型事業所の中には最近、「軽作業以外」の業種も増えつつあります。
📊 A型事業所で可能な職種の例(地域や事業所による)
| 分類 | 主な仕事内容 | 特徴・傾向 |
|---|---|---|
| 🛍️ 軽作業系 | 商品の袋詰め・箱詰め・検品・シール貼りなど | 比較的単純で身体的負荷が低い。かつての主流 |
| 🧹 清掃・施設管理 | ビル・公園・施設の清掃、備品管理など | 体を使いたい人向け。自治体からの委託も多い |
| 💻 IT・パソコン系 | データ入力、画像加工、SNS投稿代行、簡単なコーディングなど | 比較的新しい。スキル型A型。競争力がある |
| 📦 EC・ネットショップ系 | 商品撮影、商品登録、梱包・発送、在庫管理など | 小規模事業所で導入進む。やりがい重視も多い |
| ☕ 飲食・カフェ運営 | カフェ・レストランでの接客補助、調理補助 | 実践的、接客が好きな人に向いている |
| ✂️ ハンドメイド系 | アクセサリーや布製品の製作・販売など | 少数だが「作ること」が得意な人に人気 |
| 🗣️ クリエイティブ系(ごく一部) | 動画編集、ライティング、ブログ運営など | 利用者のスキル次第。事業所の体力による |
地域や設備によって差はありますが、「ネットスキルが育つ」「事業所得にも応用できる」ような内容が選べる事業所もあるのです。
僕自身、こうした仕事に出会えていたら、もう少し長くA型を続けられたかもしれません。
🔰【ここで悩んでいるあなたへ:A型が合うかチェックリスト】
以下に1つでも当てはまれば、A型就労が“選択肢”になるかもしれません。
- 朝起きて、出かける習慣を少しずつ取り戻したい
- 自分の得意・不得意を整理しながら、短時間だけ働きたい
- 家以外の場所で、人と話す機会を少し持ってみたい
- 将来的には自営・在宅ワークも視野に入れている
✅ もし「自分にもできそう」と思えたら、まずは役所の障害福祉課や就労支援センターに相談してみることをおすすめします。
「試す」ことにリスクはありません。
第3章|A型で学んだことを“自分の仕事”に活かす

僕が最終的に選んだのは、ブログとSNSを使った情報発信という「事業所得」の道でした。
A型のような“支援つきの環境”であれば、まず仕事の習慣を取り戻せる。
そのうえで、そこで得たスキルやリズムを活かして、“自分の裁量で働く道”にもつながる可能性があると思ったんです。
つまり、「A型は通過点」というより、「A型は“次の自立”への土台づくり」だった。
もちろん、A型で長く働き続けるのも立派な道です。
でも僕は、「自分で事業を育てて、自立の一歩を踏み出したい」と思った。
だから、ブログやSNSを軸に、“収益=自分の信用”という働き方を試すようになったんです。
今では、事業所得を伸ばす時間がとても有意義だと感じています。
第4章|「もらい続ける」ことが目的じゃない
僕が伝えたいのは、「年金を減らさずもらい続けるために働く」ことではありません。
働けるようになれば、自分の足で立ちたい。 でも、それまでの“支え”は遠慮なく使わせてもらっていい。
その想いです。
年金制度は「ずっと甘えるもの」ではなく、「再び立ち上がるまでの橋渡し」だと、今は思っています。
もちろん、すべての人がすぐに働けるわけじゃない。
「働けるようになったけど不安」という人にも、制度は必要です。
焦って自立する必要はない。支えられながら、成長していく。
それこそが、僕にとっての“誠実な恩返し”のかたちです。
【まとめ】この記事が届いてほしい人へ

- 「年金をもらっていると働きにくい」と感じている方
- 「制度のグレーさが怖くて、一歩が踏み出せない」方
- 「本当は稼ぎたいけど、どこまでやっていいのか分からない」方
そんなあなたにこそ、この記事が届いてほしい。
制度を正しく使うことは、ズルでも逃げでもない。
むしろ「稼げるようになってから返す」くらいの気持ちで、いまは堂々と“土台を借りて”いいんです。
そしてその土台を、自分の力で踏みしめていく。
それが、僕らなりの“再出発”なんじゃないかと思っています。
※本記事は特定の行為を推奨するものではなく、実体験と制度上の情報をもとに個人的見解を述べたものです。ご不安な方は、年金事務所または社労士等の専門家にご相談ください。
📊 ヘタゴリラの“配当記録”と“損益バトル”はXで更新中!
ブログでは語りきれない、リアルな配当金の推移や
**日経平均との“持ち株バトル”**など、日々の投資ログをXで公開しています。


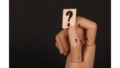
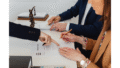
コメント