障害年金や労災年金を受給していると、「働いてはいけない」と思い込んでいた時期がありました。
調べても曖昧な情報ばかりで、どこまでがOKなのか、自分には何が許されているのかすら、よく分からなかった。
でも、僕は「就労支援A型」を利用して、月に数万円だけでも収入を得た時期があります。
それは、制度を悪用するためでも、ズルをしたかったわけでもない。
むしろ、「家族を支えたい」「社会と関わり続けたい」――そんな、素直な気持ちからの一歩でした。
【第1章】知らなかった。「働いていいのか」が一番怖かった
障害年金や労災年金には「等級」があり、それによって支給金額が変わります。
僕の場合、障害年金は1級、労災年金は2級という判定でした。
この「等級」という言葉。実は制度ごとに中身が違うのに、最初はそれさえ分かりませんでした。
- 障害年金は、日常生活での自立度や介助の必要性が判断基準。
- 労災年金は、働く能力(労働能力)をどれだけ失っているかという尺度。
たとえば「歩行が難しくても、上半身を使ってPC作業はできる」と判断されると、労災の等級が下がることもある。
逆に「一人で買い物にも行けない生活状況」なら、障害年金の等級は高く維持されやすい。
つまり、「生活の自立」と「労働の自立」は、似ているようでまったく別物なのです。
でも、当時の僕も妻も――そんな制度の違いすら理解できていなかった。
それよりも怖かったのは、「働いたら支給が止まるのでは?」という漠然とした恐怖でした。
しかもその不安は、僕の“職歴”のせいで、より大きくなっていた。
なぜなら、僕はもともと建設業の個人事業主。
現場の責任者として指示を出したり、書類をまとめたり、材料の手配をしたり。
いわゆる“動かずともできる仕事”が一部に含まれていたからです。
「少しでも仕事をしたら“能力が回復した”と見なされてしまうのでは?」
「書類を作るだけでも、労働能力があると判断されるんじゃないか?」
「年金が止まったら、家族の生活はどうなるのか……」
そんな不安が、毎日のように頭をぐるぐるしていました。
いろんな行政サイトや相談窓口も見ました。でも、答えはどれも曖昧。
「個別の事情によります」「ケースバイケースです」――そんな表現ばかり。
だからこそ、「何が許されて、何がNGなのか」がわからないまま、“働くこと”が怖くなっていたんです。
動ける時間があっても、やれることがあっても、「働く=リスク」と思い込んで、自分を止めてしまう。
それが、障害を負って最初の1〜2年の僕でした。
関連記事です。
🧩【補足】「働いたら年金は止まるの?」にハッキリ答えてみる

障害年金を受けていると、「ちょっとでも働いたら支給が止まるのでは?」という不安を抱く人が多いです。
僕自身もそうでした。でも、結論から言うと――働くこと=即打ち切りではありません。
✅判断に関わるのは“収入額”ではなく、“日常生活や就労の困難さ”
障害年金は「障害の状態」に対して支払われるものであり、「いくら稼いだか」で一律に決まるわけではありません。
たとえば:
- 障害年金1級=日常生活のほとんどに他人の介助が必要なレベル
- 障害年金2級=日常生活にある程度支障があるけれど、一部自立している
つまり、「自分ひとりで生活できる状態」に近づくと、等級が下がったり、支給停止の可能性が出てくるということです。
※ただし、労災年金や厚生年金の障害等級など、制度ごとに基準が異なります。
✅ 働いても年金が継続されやすいケース
以下のような働き方であれば、障害年金や労災年金の支給が続く可能性が高いとされています。
- 短時間・軽作業での勤務
例:週20時間未満、1日4時間以内のパートや在宅作業など - 就労継続支援(A型・B型)など、福祉的な働き方
支援を受けながら、自分の体調に合わせて働ける環境 - ごく少額の収入で、体調に波がある場合
例:月5万円程度の収入/働ける日と働けない日があるなど - 自宅でできる副業
ブログ・ライター・ハンドメイドなど、在宅でできる無理のない仕事
⚠️ 年金の“見直し対象”になりやすいケース
一方、次のようなケースでは「障害の程度が改善しているのでは?」と判断される可能性があります。
- フルタイムに近い働き方
例:週30時間以上の勤務 - 企業と雇用契約を結び、安定的な収入がある場合
定期的に給料をもらっている正社員や契約社員など - 障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳や療育手帳の場合)の更新時に、“改善”と判断されるような働き方
介助が不要な作業内容、身体能力の回復が見られる仕事など
💡 ポイントは「就労の実態」
大切なのは、「月にいくら稼いだか」ではなく、**働けている“実態”**です。
障害年金や労災年金の見直しは、以下のような点を総合的に見て判断されます。
- 仕事の内容(重労働か、デスクワークか)
- 労働時間や勤務日数(長時間か、短時間か)
- 働く中でどんな制限があるか(支援が必要かどうか)
- 日常生活でどれだけの介助が必要か
つまり、「働いた=打ち切り」ではないということです。
制度はあくまで、“その人がどれだけ生活に制限があるか”を見て判断される仕組みです。
✅僕が大事にした「判断基準」
僕が心がけていたのは、
「今の自分は、誰かの助けがなければ生活できる状態か?」
という“自分の状態”に正直であること。
元気なフリをして、年金を減らされたら本末転倒です。
逆に「働ける状態に近づいている」と感じたら、それは支給が減ることで得られる“新しい自立”だと思っています。
※この内容はあくまで僕の理解と実体験に基づくものです。正式な判断は、年金機構や主治医、社労士にご相談ください。
関連記事です。
【第2章】就労支援A型――“水が合わなかった”けれど、大きな一歩だった

実際、僕は就労継続支援A型という制度を利用して、働き始めました。
この制度は、「障害や体調の事情があっても、雇用契約を結んで働くことができる」仕組みです。
事業所と雇用契約を交わすことで、最低賃金以上の給与が支払われ、ある意味“福祉と労働の中間”のような位置づけにあります。
勤務は、月〜金の9時〜15時。仕事内容は、軽作業や事務補助など。
月5〜6万円程度の収入でしたが、「社会に戻れた」という実感を得るには、十分すぎる経験でした。
🧱 就労支援A型にたどり着くまでが、すでに「ひと仕事」だった
でも――
このA型事業所で働き始めるまでに、けっこうなプロセスがありました。
「働きたい」と思って、すぐに求人サイトを見れば何かある。
……なんて、甘いもんじゃなかった。
まずは役所に行って、「障害者総合支援法」の相談窓口に申請。
そこで言われたのが、
「相談支援専門員をつけましょう」
という話。
「専門員って何? ケアマネみたいな人?」と思いながら、紹介された支援センターに連絡を取り、面談を受けて、
さらに“サービス等利用計画”というものを一緒に作成。
そこからまた役所に申請して、受給者証が発行されるのを待つ。
この書類がないと、就労支援事業所の見学や面接すら受けられない。
つまり、
相談登録 → 面談 → 書類 → 審査 → 受給者証発行 → A型面接…
ってやってるうちに、「もういいかな…」ってなってしまう。
働くまでの道のりが、すでに“障害物レース”だった。
正直、働きたいという気持ちが冷めてもおかしくないくらい、何度も手続きや待機に直面しました。
もちろん、制度としては「無理をさせない」「ミスマッチを防ぐ」という目的があるのだと思います。
でも、こうも思いました。
「今すぐ何か始めたい」と思ったときに、このスピード感では心が折れる。
“働くこと”は、本来もっとシンプルなはずなのに。
その入口で、制度に「待った」をかけられてしまうような、そんなもどかしさがありました。
🌀 それでも通ってみて、見えてきたもの
とはいえ――
元・事業主だった自分には、どうしても“水が合わなかった”。
「言われた作業を、ただ毎日繰り返す」ことへの違和感。
周囲との価値観や働き方のギャップ。
そして、自分の裁量や工夫を発揮できないもどかしさ。
そんな積み重ねで、結局3ヶ月で退所しました。
でも――
この体験を通して「働くことは絶対にNGではない」という確信を持てたことは、何より大きかった。
制度の枠の中でも、自分にできる役割や居場所を探せるんだ、という“可能性の芽”を感じられたからです。
関連記事です。
【第3章】「稼げる力」がついたなら、それでいい
僕は正直に言うと、
**「もし将来、自分に稼げる力が戻ったら、年金が減っても、支給停止になってもいい」**と思っています。
なぜなら、年金や労災の制度は、本来**“自分の足で立てなくなったとき”の支え**だから。
裏を返せば――
自分で立ち上がれるようになったなら、それはむしろ喜ぶべきことだと思うのです。
もちろん、現実は甘くない。
体が完全に元に戻ることはないし、「フルタイムでバリバリ働ける」なんて夢物語かもしれない。
それでも、**「月に数万円でも自分の力で稼げるようになった」**という事実は、
僕にとって、過去のどんな建設現場よりも価値のある“仕事”なんです。
よく、「働いたら損」とか「稼いだら年金が減るから意味がない」といった声を聞きます。
たしかに、その気持ちも分かる。
でも、僕はあえてこう言いたい。
「それでも、“稼げる力”を育てることは、自分自身を取り戻す行為だ」と。
支給額が減る・停止されることを恐れて、
何もしないままでいるよりも――
“頼らずに生きられる力”を少しずつでも育てていく方が、きっと人生は明るい。
そして、そう思えるようになった背景には、
「今、自分がこうして制度に支えられて生きている」という感謝の気持ちがあります。
だからこそ、今この瞬間に声を大にして言いたい。
「必要なときに、必要な助けを受け取ることは、恥ではない」
「でも、受けた助けに応えるように、いつか自分の足で立つ努力をしてもいい」
【第4章】“ズルしてる”と思われないか――制度と、まっすぐ向き合う覚悟
障害年金や労災年金を受け取っていると、
「働いてるってことは、もう大丈夫なんじゃない?」
「年金をもらいながら働くのって、ズルくない?」
そんな言葉や空気を、感じたことがある人も多いんじゃないでしょうか。
僕自身も、そんな目に晒されるのが怖かった。
でも実際は、“働いていいかどうか”は「等級」や「就労内容」によって判断されるのが現実です。
軽作業で月に数万円の収入があることと、
「常勤フルタイムで一般就労する」ことは、まったく違う話。
にもかかわらず、僕ら受給者の側にこそ、「ズルしてると思われたくない」という強いブレーキがかかってしまう。
それが、制度の複雑さや、世間の理解の浅さによって生まれてしまう“空気の壁”なんですよね。
けれど僕は、自分の経験を通じて、こう考えるようになりました。
「制度に甘える」のではなく、
「制度と、まっすぐ向き合って生きる」ことが、一番の誠実さだと。
それは、申請書類を必死に書いたあの日も、
就労支援の現場で戸惑いながらも汗を流したあの日も、
そして今、こうしてブログを書いて発信を続けている今も――
ずっと変わらない僕の軸です。
もし今、「働くと支給が止まるかも」「副収入はどう扱われるの?」と不安になっている人がいたら、
僕はこう伝えたい。
“疑問を持つこと”こそが、制度と誠実に向き合っている証です。
その一歩は、きっとあなたの未来を変えてくれるはずです。
📝 まとめ|この記事が届いてほしい人へ
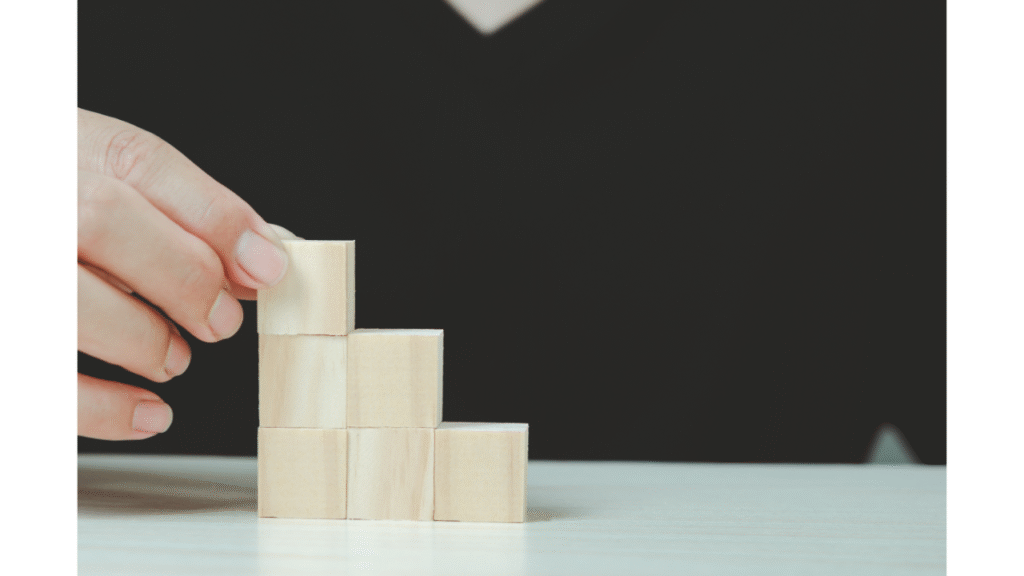
かつての僕のように、
「働いたら年金が止まるのでは?」
「副収入が出たら“ズル”だと思われるのでは?」と不安に感じている人。
あるいは、
「制度に頼ること自体が、なんだか申し訳ない」と、どこかで自分を責めている人。
そんなあなたにこそ、伝えたい。
“必要なときに、必要な支えを受け取ること”は、決してズルじゃない。
それは、社会に備えられた「生きるための仕組み」であり、
いつか“また立ち上がる”ために必要な「土台」なんだと思います。
僕はこれからも、自分の力で“立てるようになること”を目指して生きていきます。
でも、ここまで来られたのは、制度があったからこそ。
そして今も、年金や労災に支えられているからこそ。
だからこそ言えます。
あなたも、支えられていい。
そして、支えられながらでも“前に進んでいい”。
僕のリアルな言葉が、
誰かの「不安」を「前進」に変えるきっかけになりますように。
📊 ヘタゴリラの“配当記録”と“損益バトル”はXで更新中!
ブログでは語りきれない、リアルな配当金の推移や
**日経平均との“持ち株バトル”**など、日々の投資ログをXで公開しています。👉 ▶ ヘタゴリラのXはこちら



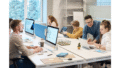
コメント